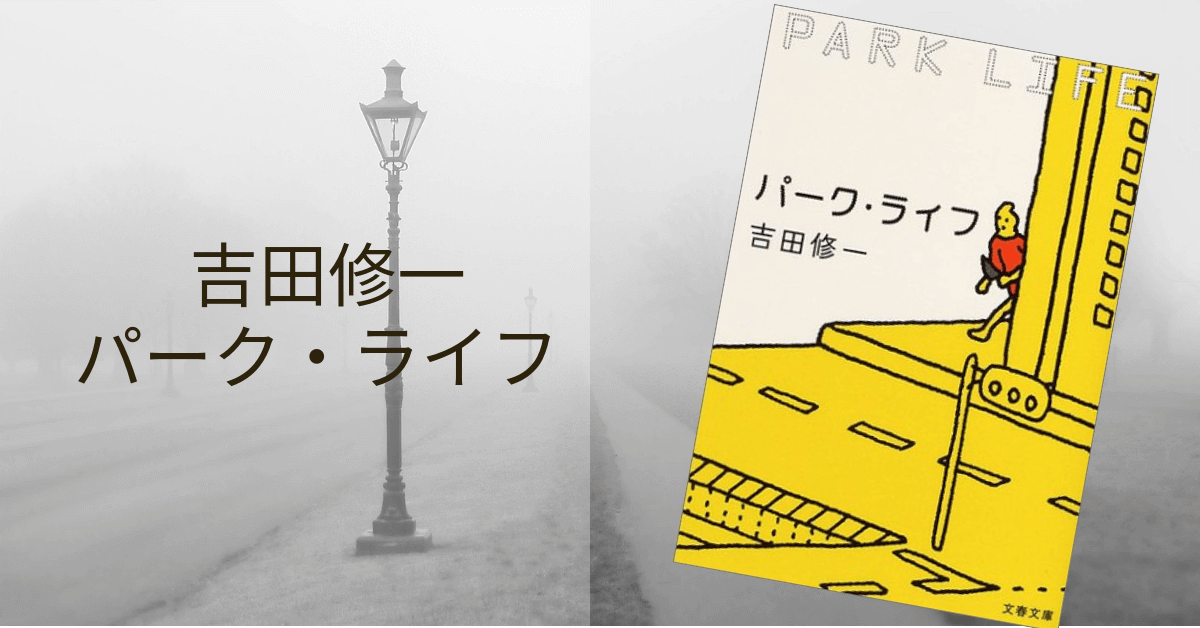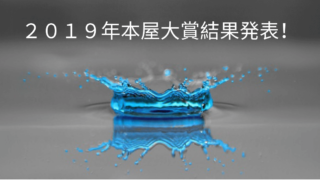第127回芥川賞を受賞している話です。
吉田修一さんといえば『悪人』、『怒り』、『横道世之介』、『国宝』など数々の著名な作品を発表している作家です。
その中でもこの『パーク・ライフ』は初期の作品に分類されるであろう短編です。
私個人的に芥川賞受賞作品は他人に勧めると意味が分からなかったと言われることも多いのですが、この話は意味わからないとなったとしても流れている雰囲気を楽しんでもらえるのではと思える作品です。
- 「人間を見る目が随所で鋭く光り、たった一行で、さりげなく決定的なインパクトを読者に与える。」(高樹のぶ子氏)
- 「いわばライフのない場所でも現代のライフの光景が鮮やかに浮かび上がっている。」(黒井千次氏)
- 「人間が生きて在るとは、どういうことなのか。そのことがまことに伸びやかに、深く伝わってくる」(河野多恵子氏)
- 「ちかごろは、この『パーク・ライフ』のように隅々にまで小説の旨味が詰まっている作品に出会うことがむつかしくなった。元来小説というものがすべてそうであるべきなのに。」(三浦哲郎氏)
当時の芥川賞選考委員の選評の抜粋です。勿論、中には否定的な意見はありましたが、点数的にもほぼ文句ない形での受賞だったそうです。
ちなみに読みやすい上に分量も短編と言えるほど少ないのでさくっと読めてしまうと思います。(『パーク・ライフ』文春文庫には、別に短編「flowers」も収録されています)
現在、書店の平積みになっているコーナーで名前を見ない日がないほど活躍されている作家の芥川賞受賞作。
私は昨年人に勧められて手に取ったのですが「これは面白い!」と思いました。
Contents
あらすじ
日比谷線で出会ったぼくと彼女は度々日比谷公園で会って話をします。
そこにはゆるい恋愛感情と微妙な変化、微妙な距離感があります。
春風流れる公園でスタバのコーヒーを飲んだり、雑貨屋の人体模型を眺めてみたりして過ごす日常があります。
なんとなくとも思えるような日々や気持ちと男女の微妙な距離感が描かれた小説です。
パーク・ライフの感想
この小説はスタバとか日比谷線とか日比谷公園とか離婚しそうな知人の夫婦とか舞台、設定があって、リアルっぽく流れる時間の中で、少し気持ちが切り替わるような瞬間が描かれた話のように私は感じました。
ラストシーンがよかったです。
なにげない会話の中で少し気持ちの波があって何かを決断したり頑張ろうと思えたりする瞬間が好きです。
例えば公園でぼーっとしていたり、コーヒーを飲んでリラックス気分になったり、少し仲良い人に自分の話をしてみたり、多分、人が前向きになれて一歩踏み出す瞬間て何気ない日常での一コマだと思います。
それは誰かに明言を掛けられたり、あるいは大切な人が亡くなったり、どん底に落ちたり、逆に上がったり、そういう劇的なことであることの方が少ないです。
劇的な物語は面白いのですが、こうやってしみじみ文章を楽しめるような小説は芥川賞の選評の言葉を借りるなら「小説の旨味」だろうと思いました。
終わりに
弟に勧められて読んだ小説です。
「どんな話?」と聞くと「何も起こらない話」と言われ、はじめ、なんだそれと思いました。
そして確かに何が起こったわけでもありませんでした。
でも何で勧めてくれたのかは分かりました。
現実の中で頑張ろうと思える瞬間が小説を読んでリアルに感じられることができて、いい余韻を味わうことができました。