アート小説の最高峰! 原田マハさんがゴッホとともに闘いぬいた傑作!
ゴッホは日本人が知る西洋の画家の中で最も有名な人物と言っても言い過ぎではないと思います。
小学生時代の教科書にゴッホの『タンギー爺さん』が載せられていてとても印象に残っています。
背景が浮世絵だったことも印象的な理由でしたが、それよりもたくさんの色がタンギー爺さんの温かさを表しているようでとても好きでした。
絵と写真を比べることはできませんが、絵によって伝わるモデルの内面もあるのだと分からせてくれた体験でした。
その絵を描いたフィンセント・ファン・ゴッホが37歳で亡くなっていたとはその時は想像できませんでした。
ゴッホはどんな人生を送ったのか。
本作は史実をもとにして原田マハさんが自由に創作した物語です。
ゴッホの壮絶な生涯を描いたアート小説の最高峰です。
簡単なあらすじ・説明
1886年、栄華を極めたパリの美術界に、流暢なフランス語で浮世絵を売りさばく一人の日本人がいました。
彼の名は、林忠正。
その頃、売れない画家のフィンセント・ファン・ゴッホは、放浪の末、パリにいる画商の弟・テオの家に転がり込んでいました。
兄の才能を信じ献身的に支え続けるテオ。そんな二人の前に忠正が現れ、大きく運命が動き出していきます。
史実を元にして原田マハさんが自由に創作したフィクションです。
綴られる物語の要所要所に史実に残るエピソードが描かれています。
ここからネタバレ注意!
たゆたえども沈まずの感想(ネタバレ)
林忠正と重吉
林忠正は明治期、パリ万博で日本を知ったフランスにわたり、日本美術を世界に売り込んだ人物です。
開国間もない日本は当時のフランスにとっては東洋の小さな島に過ぎません。
しかし、そこに切り込み、日本美術を売り込んだ林忠正の存在は現代の日本での知名度以上に大きいです。
実際には林忠正とゴッホとに交流があったかはわかってはいません。
ただ間違いなく日本美術はゴッホの芸術に影響を与えていて、同時代に日本美術を売り込んだ林の存在があるということは直接交流があったかは分からなくてもそれぞれの交錯した想いの上に私たちがゴッホの絵画を見ての感動があるのだと言えます。
そしてこの物語は史実やゴッホの描いた絵画という記録を元に実際と同等以上の説得力があります。
二人の日本人が花の都・パリで評価を受けるべき日本美術を売り込んでいきます。
そして二人は評価を受けるべき絵画にも出会います。
それはフィンセント・ファン・ゴッホの絵です。
林忠正は少し距離を置いたような位置で、重吉はフィンセントの弟のテオとの密接な交流からフィンセントの様子を林に繋ぐような位置取りにいます。
どの人物でも変わらないのは見方はそれぞれ違ってもフィンセントの才能を信じているということです。
この4人の熱い想いがそれぞれに作用しあって人生が動いていきます。
テオの仕事の背景もあり、なかなか評価されることのなく苦しい日々を送っているテオに林がフィンセントの絵の感想を漏らす場面は胸にこみ上げるものがありました。
それは『タンギー爺さん』の絵画を観た場面でした。
――いつのまに、兄さんはこんな絵を……。
言葉を失って、テオは絵の中のタンギーとみつめ合った。そうするうちに、ふいに涙が込み上げてきた。
テオは顔を逸らした。泣いてはいけない、けれど、涙がこぼれてしまいそうだった。
「あなたの兄上は……」
ふと、忠正の静かな声が耳に届いた。
「……とてつもない画家かもしれない」
テオは、振り向こうとして、振り向けなかった。
涙があふれて、頬を濡らしていた。泣き顔を誰にも見せたくはなかった。
四人の魂が共鳴していく場面が私達を物語の世界に引き込んでいきます。
フィンセントとテオの生涯
ゴッホの絵は生前一枚しか売れなかったといいます。
そしてテオはフィンセントを経済面含めてずっと支えてやってきました。
フィンセントはテオのお荷物になっているという気持ちを拭えなかったでしょうし、テオはそんなつもりがなくても自身の目の前の物事によってフィンセントの気持ちを慮ることができないこともあります。
二人の気持ちはすれ違い、私が思う最悪な方向へと流れていきます。
ゴッホ兄弟はとても繊細で、それでいて目の前の物事に対して本気でした。
本気過ぎるくらいの気持ちで目の前で起きる出来事にぶつかり打ちのめされてしまうように思えました。
すごく不器用で真っすぐです。
最後の「僕たちは、いつまでも、どこまでも一緒だ」というテオの言葉に頷いて言ったフィンセントの言葉が、
「――このまま死ねたら……いいな……。」
苦しい。
画家と画商の兄弟。
でも絵を通して二人は身体を共有しているように生きていました。
そしてわずか半年後にフィンセントの後を追うテオの生涯をどう感じればいいのでしょうか。
私にはわかりません。だけど(この物語はフィクションではありますが)彼らの残した絵画を感じてみたい気持ちに駆られました。
たゆたえども沈まず
花の都・パリ。
しかし、その中心部を流れるセーヌ川が昔から何度も氾濫し、街とそこに住む人々を苦しめてきました。
それでもパリはいかなる苦境に追い込まれようとも決して沈みません。
どんなときであれ、何度でも。流れに逆らわず、激流に身を委ね、決して沈まず、やがて立ち上がる。
そんな街。
それこそが、パリなのだ。
「たゆたえども沈まず」はゴッホ兄弟の想いもでしょう。そして林・重吉の想いも含めて。
読み終わって冒頭の場面を読み直します。
時系列的には一番先の描写です。
かつてテオに送った林の手紙。
兄のフィンセントの絵が必ずいつか世界が認める日が来ることを信じてテオに「強くなってください」と励まし、林も重吉も戦い続けていることを綴った手紙です。
その手紙は風で流れて川の真ん中に落ちても沈まずたゆたいながらも流れていきます。
悲しい物語かもしれません。でも物語を読み終わって私はそれでも生き続けている想いが今現在の世界で叶えられていることを嬉しく思いました。
たゆたえども沈まずの感想まとめ
読み始めていつのまにか200ページくらい読んでいて、わくわくとは違うのですが自分がこの本に没頭していることに気づきました。
ゴッホ兄弟が日本と関わりある画家だということは物語を身近に感じる要素かもしれませんが、それ以上に林や重吉、ゴッホ兄弟の生きる力を感じたからでした。
兄で画家のフィンセント・ファン・ゴッホは37歳で亡くなり、画商のテオドルス・ファン・ゴッホは33歳で亡くなりました。
人生を突き詰めて(突き詰め過ぎてとも言えるかもしれない)生きた日々が詰まっていて、勝手に悔しくなり、辛くなりました。
人生の幸せな時間が長い人が結果的にいい人生なのか、それとも最終的な喜びを求め続けていくような日々がいい人生なのでしょうか。
色んなことをさらっと流して楽しく楽しくやっていくこともいいかもしれません。
でも亡くなった後に絵画が大きな評価を得たゴッホの生涯はそこには濃密な生きた時間が流れていて、軽はずみには言えないけどすごいと思うし、憧れに近い気持ちを抱きます。
だからフィンセントもテオも人生の終わりを迎える場面が苦しかったです。
スケールの大きな物語が身近で美しく悲しく感じられる物語です。
また、10月から来年にかけて上野・兵庫でゴッホ展が始まるので、小説でこの時代の空気に触れてゴッホ展を鑑賞するのもいいのではないでしょうか。
個人的に本当に楽しみにしている美術展です。
あー、もう終盤辛かった。でも読んでよかった。



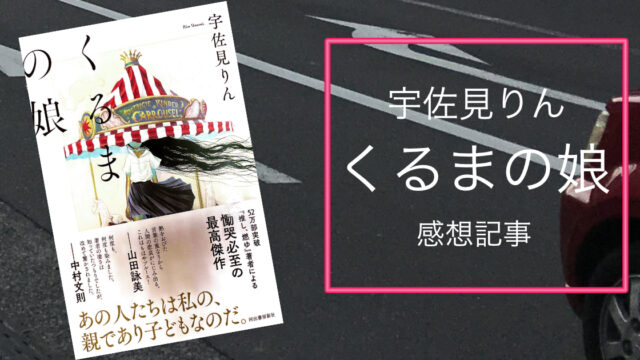
































[…] […]
[…] […]